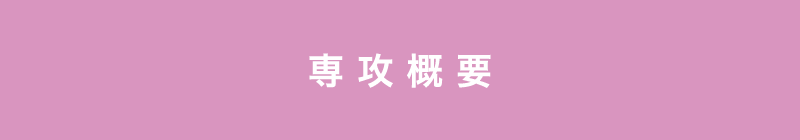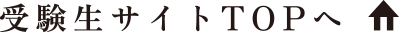- [取得免許状]
-
- ●養護教諭一種
- ●中学校教諭一種(保健)
- ●高等学校教諭一種(保健)

両方に携われる養護教諭に魅力を感じました。
子どもの頃から医療や看護の仕事に興味がありました。その一方で、中学生の時に出会った先生が生徒の成長を一番に考えて接してくれた姿も印象に残っていて、心身のケアと教育の両面から子どもを守り育てる養護教諭をめざすようになりました。大学選びでは教員採用試験の合格実績に注目し、名古屋学芸大学に決めました。


1年次は身体のしくみや子どもの発達、学校保健、教職の基礎知識などを幅広く学び、養護教諭に必要な土台をつくりました。「養護概論Ⅰ・Ⅱ」では、養護教諭の実務経験を持つ教員から具体的な職務について体験談を交えながら教わりました。保健室での対応や保健指導だけでなく、校内の水質や空気の衛生管理、感染症の対応など、子どもからは見えない部分の職務の幅広さや、かかわる人の多さに驚きました。また医師や看護師の免許を持つ教員から学ぶ「身体のしくみⅠ」や「看護学Ⅰ」では、専門知識とともに、子どもの命を預かる責任の大きさも理解でき、養護教諭になる決意が少しずつ固まっていきました。



2年次は、1年次に学んだ知識をもとに、実践的なスキルを養う演習に取り組みました。「救急処置」では、提示された事例に対して問診から処置まで一連の流れを実践。症状からあらゆる可能性を検討し、適切に対処する方法を学びました。「学校保健演習」では、保健室を再現した実習室で健康診断の運営や正確な測定法を学んだほか、5分間の保健指導も行いました。また、保健科教諭の免許状取得に向けて、教職課程での模擬授業が始まり、効果的な指導法を理解するとともに、子どもの前で授業を行うイメージがつかめました。



3年次は授業の専門性がより深まりました。「健康相談演習」では具体的な事例を想定して支援計画をつくり、ロールプレイ方式でカウンセリングを実施。「保健科教育法Ⅱ・Ⅲ」では模擬授業の対象を中学生、高校生と変えながら授業内容や教え方を工夫しました。そして小学校での「養護実習」では、保健室を訪れる児童が一人ひとり異なるからだの不調を訴えるため、それに対応できる臨機応変さを学んだほか、6年生のクラスで保健指導も行いました。簡単な実験などを取り入れて「姿勢を伸ばすことの大切さ」を教えると、指導後の児童の姿勢がとても良くなり、指導の意義や効果と教える楽しさを実感することができました。
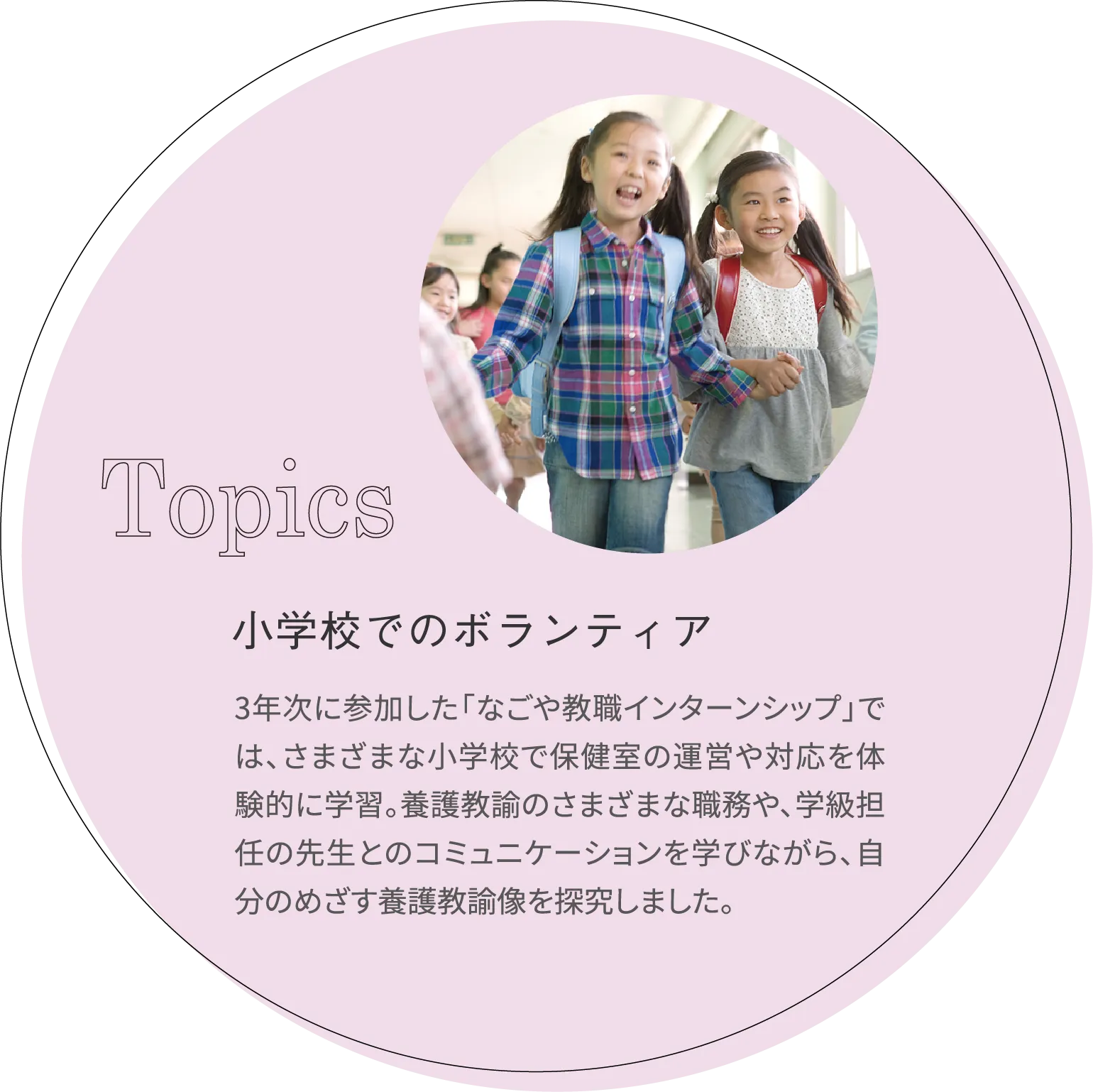


4年次の中学校での「教育実習」では、1年生の生徒に性や生命についての授業を行いました。デリケートな内容でしたが、教材に私自身の乳幼児期の写真を用いるなど工夫を施し、親しみやすいムードで学んでもらうことができました。またこの実習で学級担任の職務も経験したことで、担任の視点から養護教諭に求められる対応を理解できたのも大きな収穫でした。それと並行して、教員採用試験の準備も本格化しました。全体で行う対策講座に加え、めざす自治体に合わせて対策を行う個人・集団面接や論作文の講座では、先生方が個別に何度も指導してくださり、試験本番にも落ち着いて臨むことができました。

※掲載内容は在学時に取材した2024年2月末現在の情報です。




- [取得免許状]
-
- ●養護教諭一種
- ●中学校教諭一種(保健)
- ●高等学校教諭一種(保健)

養護教諭に憧れました。
中学3年生の時に保健委員になり、保健室で養護教諭が他の生徒と接する姿を見るうちに、憧れるようになりました。高校3年生になって名古屋学芸大学のオープンキャンパスに参加した時、先生や先輩が親身になって相談に乗ってくれ、学校保健実習室や看護学実習室などの施設も充実していたので、ここで学びたいと思いました。


1年次は、子どもの発達や、養護教諭の職務、教育の基礎知識などを学び、養護教諭をめざすうえでの土台を固めました。医師免許を持つ先生から子どもの身体や病気について学ぶ「身体のしくみⅠ」や、養護教諭として豊富な経験のある先生から現場の実務などを学ぶ「養護概論Ⅰ・Ⅱ」を通して、養護教諭の責任と役割の大きさを実感しました。多くの授業で、学んだ内容について議論する時間が設けられ、自分ならどうするか、自分はどんな養護教諭になりたいのかを考えさせられました。経験や知識の幅、視野を広げるため、中学校と高等学校の保健教諭の免許状の取得もめざすことに決め、海外研修にも参加しました。



2年次は、保健室でのケアや保健指導など、養護教諭のさまざまな職務に対応した技術を学ぶ演習科目が増えました。「救急処置」の授業では、提示された具体的な事例について、問診や触診、声掛け、処置まで実践。その後、先生から改善点や別のアプローチ、対処の仕方を教えてもらい、場面に応じた柔軟な対応を学ぶことができました。「保健科教育法Ⅰ」では、指導案をつくり、初めての模擬授業に挑戦。緊張して思い通りの授業はできませんでしたが、反省点を意識して練習や準備を行うと、徐々に自信が持てるように。また仲間の行う模擬授業からも多くのことを学べました。
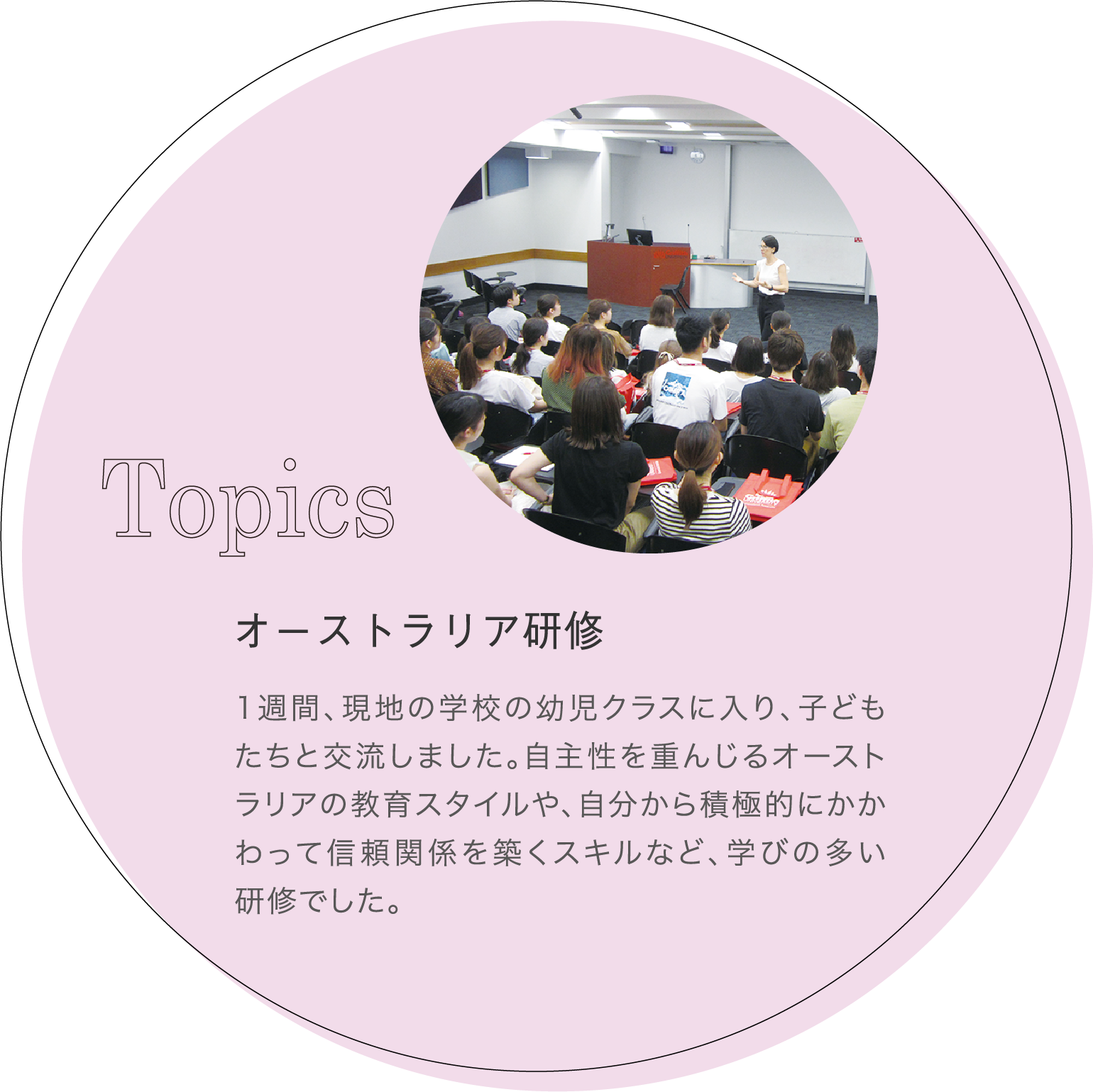


小学校での「養護実習」では、健康診断の運営や保健室の経営、子どもへの対応、保健指導に取り組みました。保健指導では、1~6年までの全クラスで、手洗い指導を実施。学年ごとに教材を変えながら、理解度や反応の違いを肌で感じました。また保健室では、ケガや病気の状態や、そうなった原因を子どもたち自身に話してもらうよう促す養護教諭の姿勢に、教育者としてのあり方を教えられました。一方、大学での授業もより高度になり、例えば、心因性の不調を抱える子どもへのアプローチや、スクールカウンセラーと連携した支援など、具体的な事例を検討する機会が増えました。
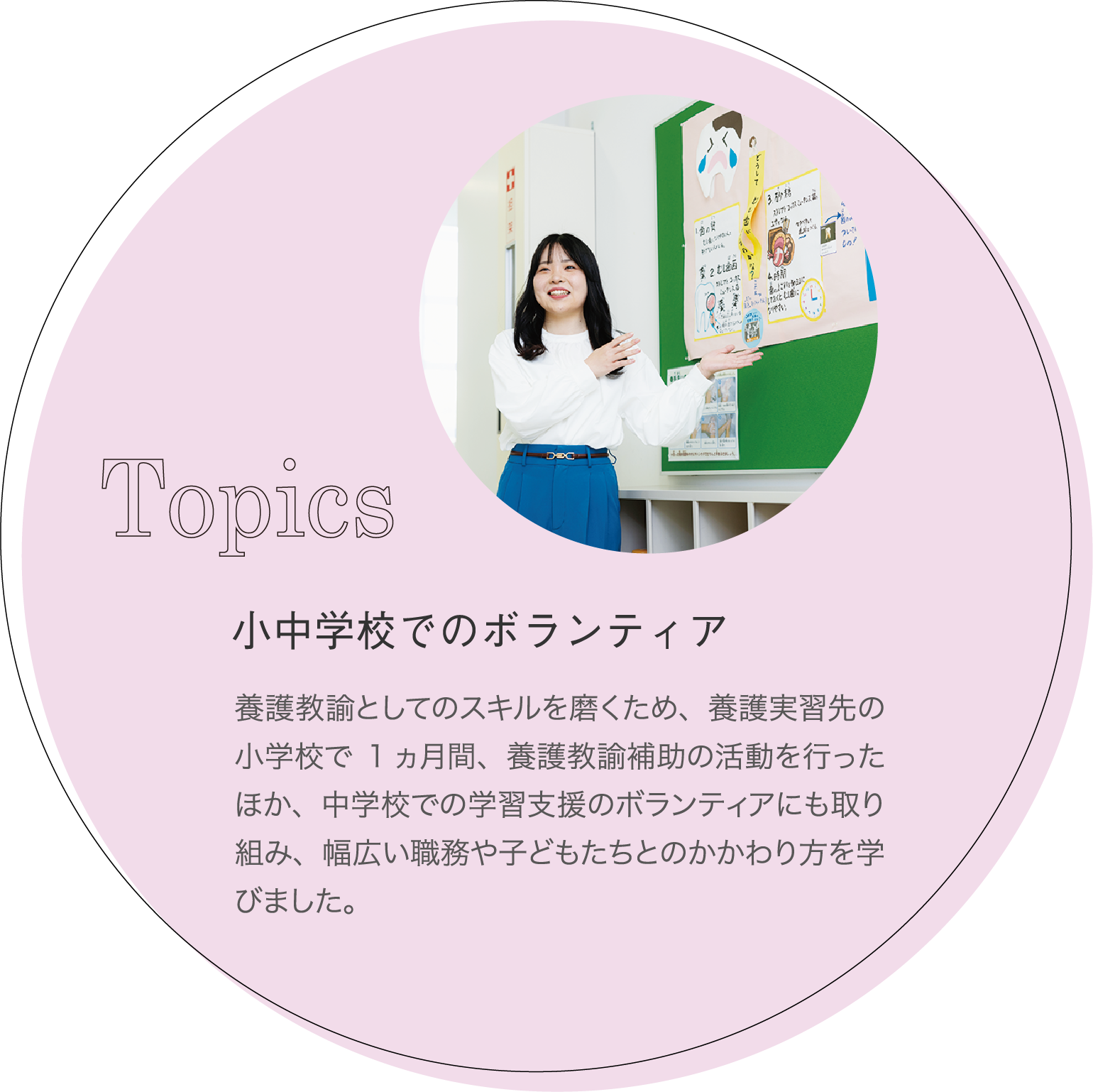


4年次は、教員採用試験に向けた取り組みが本格化しました。自治体ごとに行われる採用試験対策講座に加え、個人・集団面接や場面指導、模擬授業についてもさまざまな先生に指導していただきました。また、空き時間や放課後に、仲間と協力しながら勉強や面接の練習を行うなど、モチベーションを維持しながら取り組めたので、本番で力を出し切ることができました。その後の中学校での「教育実習」では、生徒が主体的に学べるようグループワークを取り入れたねらい通りの授業ができ、自信がつきました。卒業後は、子どもたちが生涯健康で過ごせるよう、健康教育に力を入れていきたいです。

※掲載内容は在学時に取材した2023年2月末現在の情報です。