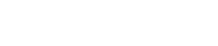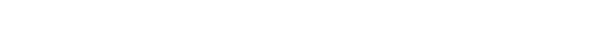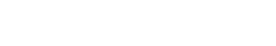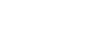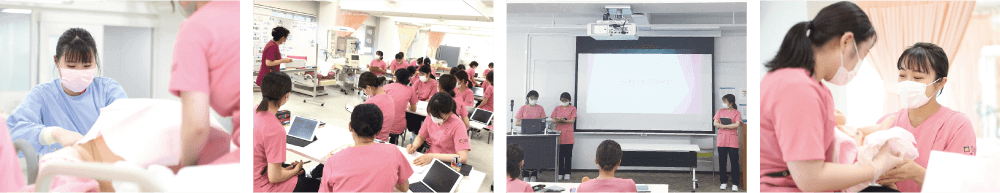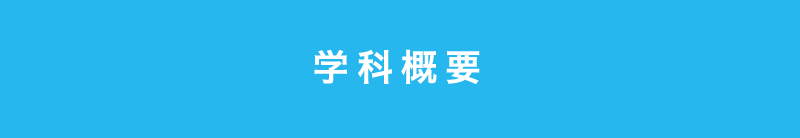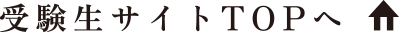- 前身は「国立病院」です。安定した母体と公務員に準ずる待遇が看護師としての人生をしっかりと支えます。
- 現任教育プログラム(職場での教育制度)が充実しているため、医療技術や看護レベルの進歩に合わせて自分自身も成長し続けられます。
- 全国に140の病院ネットワークがあり、家庭の事情などで転居する場合でも、国立病院機構の病院へ転勤することで、役職や給与等の待遇が引き継がれます。
- 2025年3月卒業生実績
-
-
就職先内訳
-
就職決定率
-
主な就職先(2022年3月~
2025年3月卒業生実績)- 国立病院機構
-
- 名古屋医療センター
- 豊橋医療センター
- 東名古屋病院
- 鈴鹿病院
- 大阪南医療センター
- 国立研究開発法人
-
- 国立長寿医療研究センター
- 国立国際医療研究センター病院
- 国立成育医療研究センター
- 大学病院(国公立)
-
- 名古屋大学医学部附属病院
- 名古屋市立大学病院
- 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
- 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
- 名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院
- 三重大学医学部附属病院
- 京都府立医科大学附属病院
- 公立病院
-
- 愛知県がんセンター
- 公立陶生病院
- 岡崎市民病院
- 春日井市民病院
- 小牧市民病院
- 碧南市民病院
- あいち小児保健医療総合センター
- 豊橋市民病院
- 一宮市立市民病院
- 稲沢市民病院
- 大垣市民病院
- 岐阜県総合医療センター
- 岐阜市民病院
- 中津川市民病院
- 市立四日市病院
- 静岡県立こども病院
- 兵庫県立尼崎総合医療センター
- 三田市民病院
- 東京都健康長寿医療センター
- 公的病院
-
- 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院
- 国家公務員共済組合連合会 名城病院
- 地域医療機能推進機構 中京病院
- JA愛知厚生連(安城更生病院、江南厚生病院、豊田厚生病院、海南病院)
- 中部ろうさい病院
- 旭ろうさい病院
- 岐阜県立多治見病院
- 鈴鹿中央総合病院
- 日本赤十字社医療センター
- 大学病院(私立)
-
- 愛知医科大学病院
- 藤田医科大学 岡崎医療センター
- 東邦大学医療センター 大森病院
- 国際医療福祉大学 三田病院
- 慶応義塾大学病院
- 順天堂大学医学部附属浦安病院
- 一般病院
-
- トヨタ記念病院
- 刈谷豊田総合病院
- 名古屋記念病院
- 名古屋掖済会病院
- 八事病院
- 一宮西病院
- 中部国際医療センター
- 鈴鹿回生病院
- 大同病院
- 聖隷浜松病院
- 名古屋セントラル病院
- 桶狭間病院
- みなと医療生活協同組合 協立総合病院
- 北医療生活協同組合 北病院
-
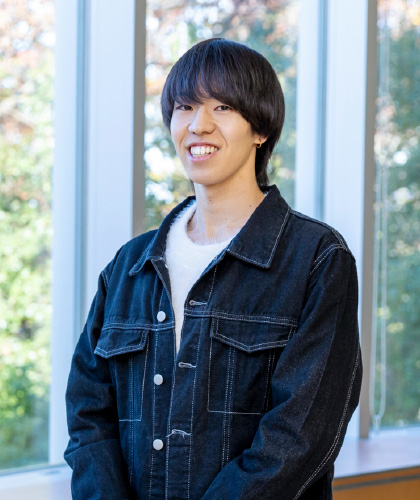
詳しく見る
詳しく見る閉じる
キャンパスに隣接する名古屋医療センターでは、1年次の「基礎看護学実習1」を皮切りに多くの実習を行いました。その際どの診療科でも感じたのが、看護の質の高さです。素早く正確な状況判断や処置はもちろん、患者さんの精神面への配慮も細やかで、自分のめざす看護師像を確立させることができました。進路を決めた3年次からは名古屋医療センターの奨学金制度も利用し、アルバイトを減らして実習に専念できたことも有難かったです。名古屋医療センターをはじめとした国立病院機構の病院は専門看護師などの資格取得支援も手厚く、教育制度も充実しているので、就職後もキャリアアップをめざしたいと思います。
※掲載内容は在学時に取材した
2025年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
4年間を通じて国立病院機構の病院を中心に、さまざまな病院で実習を行いました。印象深いのは、「精神看護学実習」で担当した、コミュニケーションに課題を抱える患者さんです。最初は挨拶も上手くいかず悩みましたが、同行した先生に助言をいただきながら距離を縮めると、少しずつこころを開いてくれ、最後は院内のイベントに参加してくれるまでになり、自信がつきました。また各病院での実習を通して、就職先は大学での学びをすべて活かせる総合病院であることに加え、長く働ける制度や環境が整う大同病院を志望しました。卒業後は、患者さんや周囲のスタッフに信頼される看護師をめざします。
※掲載内容は在学時に取材した
2025年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
英語が好きなこともあり、姉妹校である名古屋外国語大学の教員による「臨床看護英語」などの語学科目も積極的に受講しました。看護と英語の接点を見つけたのはオーストラリア研修。自分の言葉で上手く伝えられないと、もし体調が悪くなった時に医療機関で症状を説明できないと気づいたのです。また、4年次の「国際看護学演習」では、保健医療が発達していない国々の現状と、その国の宗教や生活習慣を尊重した看護の重要性も学びました。こうした経験が決め手となり、日本で暮らす外国人の患者さんをケアするため、国際部をもつ国立国際医療研究センター病院を就職先に選びました。在留外国人の視点に立ち、適切なケアができる看護師をめざします。
※掲載内容は在学時に取材した
2024年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる看護学科には、名古屋医療センターに勤務する医師から講義を受ける機会があります。例えば「病態治療学」では患者さんの症例や手術の様子など、具体的なエピソードを交えた解説だけでなく、実際に使われている医療器具に触れながら操作方法や使用シーンについて学ぶことができました。看護学実習で患者さんとコミュニケーションをとりながらスムーズに治療やリハビリにつなげられたのも、医師による講義を受け、事前に医療現場をイメージできていたからだと思います。卒業後は、実習を通して自分が働く姿を重ねることができた名古屋医療センターに就職します。どんな患者さんにも柔軟に対応できるよう、現場で経験を積んでいきたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2023年2月末現在の情報です。閉じる
-
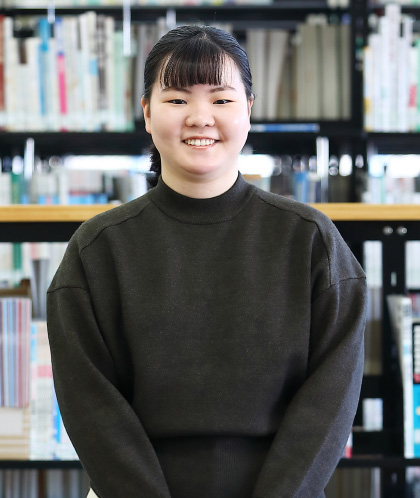
詳しく見る
詳しく見る閉じるコミュニケーションの大切さを実感したのは、1年次の「基礎看護学実習1」でした。初対面の患者さんと接するとき、最初はぎこちない雰囲気でしたが、「コミュニケーション論」で学んだ通りに目を合わせながら相槌を打ち、私自身が親身になりたいという気持ちを表し続けました。すると徐々に信頼関係を築くことができ、患者さんから家族への感謝の気持ちや普段の暮らしについて話してくれるようになりました。接し方を工夫することで、患者さんの表情を明るくすることができた経験が自信につながり、コミュニケーション力を私自身の強みにできたと思います。卒業後は患者さんを心身ともに支え、笑顔にできる看護師をめざします。
※掲載内容は在学時に取材した
2023年2月末現在の情報です。閉じる
-
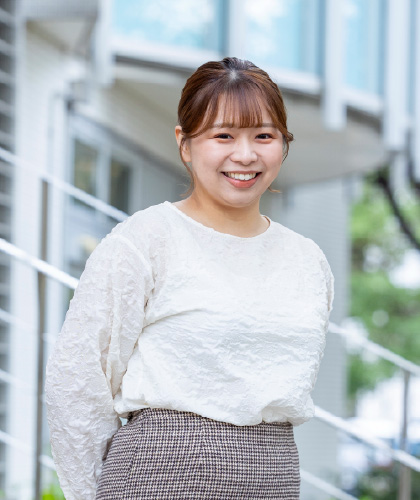
詳しく見る
詳しく見る閉じる
看護師である母から、「病院と隣接する大学なら移動の負担が少なくて実習に集中できるよ」と勧められ、名古屋学芸大学に入学しました。現場経験豊富で面倒見の良い先生方ばかりで、「急性期看護」など領域別の各講義ではポイントをまとめた資料をつくってくださり、実習の際、ひと目で予習や確認ができました。私は子どもが好きで、当初は小児看護に興味があったのですが、領域別の実習を通して在宅看護にも興味が広がり、ゼミナールでは地域在宅看護を研究。就職先も、自分の暮らす地域に根差した総合病院に決めました。卒業後は多様な診療科で知識とスキルを高め、将来は訪問看護師として患者さんとご家族を支えていきたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2025年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
私にとって4年間の学びの柱は、キャンパスに隣接する名古屋医療センターでの看護学実習です。特に印象的なのは、1年次の「基礎看護学実習1」。症状の軽い患者さんを担当したのですが、話してみると不安で眠れないことがわかり、どんな患者さんにとっても病院は非日常の場で、看護師の気配りが精神面の支えになることを実感しました。その後も名古屋医療センターのさまざまな診療科で実習を行うなかで、症例数の多さや充実した医療体制はもちろん、私たち学生や新人看護師に対して丁寧に指導してくださる環境に触れ、ここでなら意欲的に仕事に取り組めると確信しました。入職後は着実に経験を積み、患者さんの心身を支えられる看護師をめざします。
※掲載内容は在学時に取材した
2024年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
1年次の「解剖生理学」で人体の仕組みを学び、2年次の「病態治療学」でさまざまな病気の症状や治療法を学ぶなど、早期に看護の基礎となる知識を身につけたことがその後の看護学実習で役立ちました。例えば「急性期実習」で手術を受ける患者さんを担当したのですが、手術中の体位や憂慮すべき合併症など、必要な知識があらかじめ頭の中に入っていたので、落ち着いて対応することができました。こうした経験から急性期の患者さんにもっと深くかかわり、最適なケアを行いたいと考えるようになりました。卒業後は手術室への配属を希望しています。全身の疾患に対応できる看護技術を身につけた上で、さまざまな医療現場を経験し、成長し続けていきたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2024年2月末現在の情報です。閉じる
-
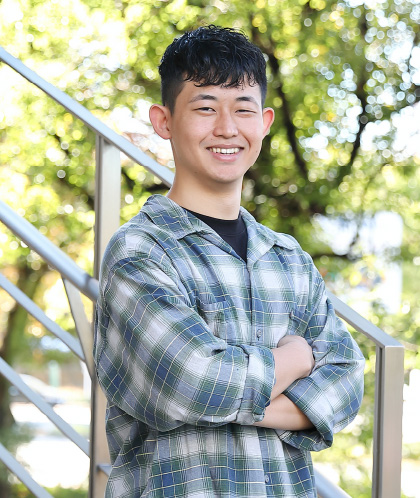
詳しく見る
詳しく見る閉じる認知症の患者さんをケアする看護師になりたいと思ったのは「急性期実習」がきっかけでした。この実習で担当した患者さんは入院したばかりで、認知症の影響からか、環境の変化に戸惑いと不安を感じている様子でした。不安を取り除くため実践したのが「成人・老年看護学概論」で学んだ対話の方法です。まずは私が味方であるとわかってもらうために、若い頃の話や楽しい思い出話を頷きながらしっかり聞くことに。すると、徐々に安心した顔を見せてくれるようになりました。実習期間が短く感じ、より専門的なケアをしたいと思い、認知症対応病棟を備えた国立長寿医療研究センターへの就職を決めました。認知症認定看護師の資格取得も視野に入れ、経験を積んでいきたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2023年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
呼吸器科の病棟に勤務し、肺気腫や肺がん、肺炎などの患者さんを中心に担当しています。症状や必要なケアは患者さんごとに異なるので、カルテを読み込み、積極的にコミュニケーションを取りながら最適な看護を考えます。例えば、化学療法中の患者さんの場合、アレルギー症状や副作用を随時チェックするほか、食欲が落ちていたら管理栄養士と連携して栄養摂取量を維持できるような食事内容に変更するなど、他の医療スタッフと協力しながら支えていきます。また、精神面のサポートも大切で、手術を控えた患者さんには事前に手術前から回復までの流れを丁寧に説明して不安を和らげ、身体機能が低下した患者さんにはできることを一緒に探して自信を取り戻してもらうなど、一人ひとりの気持ちに寄り沿い、退院まで支え続けます。患者さんが元気になる姿を見られるのは何よりうれしく、退院時に患者さんやご家族に感謝していただけるのは本当にありがたいこと。今後もこの病棟でスキルを磨き、他の診療科も経験しながら、看護師として進む道を見極めたいです。

祖母が看護師をしていたこともあり、幼い頃から看護師になりたいと思っていました。大学の学びはとても実践的で、例えば「病態治療学」では、名古屋医療センターの現役の医師が、実際の手術の動画を見せながら解説してくれるなど、今考えてもとても恵まれている環境でリアルな医療知識を学べました。看護学実習も1年次から始まり、最初は患者さんへの挨拶にすら苦労するほど人見知りだった私も、3年次の実習の頃にはどんな患者さんとも躊躇なく会話できるようになり、各領域の専門スキルに加え、患者さん一人ひとりの背景を理解したうえで最適な看護を考える力が身につきました。実習の半分以上を隣接する名古屋医療センターで行い、実習後すぐに大学に戻って調べ物や翌日の準備ができたことも、名古屋学芸大学ならではの学びやすさだと思います。就職先を名古屋医療センターに決めたのも、実習を通して高度な看護内容や尊敬できる看護師の先輩に出会えたから。慣れた環境で気持ちに余裕を持って、看護師のスタートを切ることができました。

※掲載内容は2025年3月現在の情報です。
閉じる


就職活動やキャリア形成に役立つ各種資格の取得を奨励するため、対象となる60種類以上の資格において、
取得(合格)した資格の受験料全額を支給します。在学中に1人4回まで利用できます。
- 看護学科に関連する
対象資格の一例 -
- 防災士
- 救命救急講習 ハートセイバー
CPR AEDコース - 救命救急講習 ハートセイバー
ファーストエイドコース - 救命救急講習 BLSプロバイダーコース


多職種が連携する医療現場、多様な属性の個人を対象とする看護の場において、幅広い専門知識により看護を多角的な視点で捉える能力が求められます。本研究科では、高度な看護専門職、医療機関の管理職、大学教員などをめざす「研究コース(2年制)」と、保健所や保健センターで地域住民の保健指導や健康管理を担う「保健師」の資格取得をめざす「保健師養成コース(2年制)」を設置しています。


-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
祖母が看護師で、私自身も子どもが好きだったので、助産師になることを視野に入れ名古屋学芸大学に入学しました。「母性看護学実習」では初産婦の方を担当し、妊娠中の心身の変化と看護法を学びました。その際、妊婦の体調面だけでなく精神面もケアする助産師の姿に憧れ、この道に進む意志が固まりました。助産学を専門的に学べる教育機関が減少するなか、名古屋学芸大学は別科助産学専攻がある恵まれた環境です。ゼミナールも別科助産学専攻への入学希望者が多い母子看護研究室を選び、仲間と支えあって学びを深め、学内選抜入試に合格することができました。別科入学後はハイリスク出産やNICU(新生児集中治療室)での看護を学び、あらゆる妊婦さんを支えられる助産師をめざします。
※掲載内容は在学時に取材した
2025年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
命の誕生に携わる助産師は、中学生時代から憧れの職業でした。学部入学時から別科助産学専攻入学を希望していたこともあり、子どもや出産にかかわる科目には特に力を入れました。「母性看護学実習」では、新生児が誕生する瞬間に立ち会わせていただき、赤ちゃんとお母さんが初めて対面する姿に涙が出そうなほど感動しました。同時に、大きなライフイベントにかかわる責任の重さも実感しました。別科入学にあたっては担当教員のアドバイスを受けながら母性看護学領域を重点的に復習し、学内選抜入試に合格することができました。入学後は妊娠から出産、その後の生活に至るまでフォローできる知識とスキルを身につけていきたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2023年2月末現在の情報です。閉じる
-
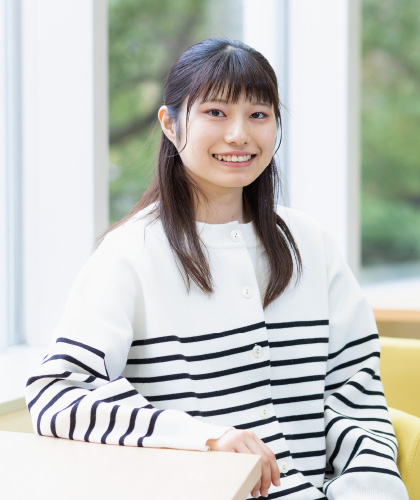
詳しく見る
詳しく見る閉じる
3年次の「母性看護学実習」で出産の現場に立ち会いました。そこで目にしたのは、お産のすべてを取り仕切る助産師の姿。出産リスクの高い妊婦さんだったのですが、助産師の優しい声掛けや適切なケアがあり、リラックスして出産に臨めていました。こうした経験から、命の誕生の瞬間を支える助産師をめざそうと決意。その後は母性学のゼミナールで専門的な知識を深め、助産師志望の仲間と高め合いながら勉強し、選考試験に合格することができました。別科助産学専攻入学後は、実習を通じて助産学のスキルを磨き、出産時だけでなく、命の教育や性教育など、女性の心身の健康を生涯にわたって支援できる助産師をめざします。
※掲載内容は在学時に取材した
2024年2月末現在の情報です。閉じる