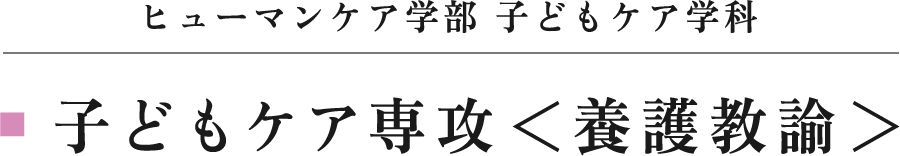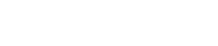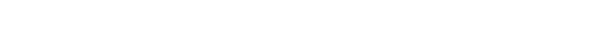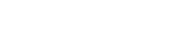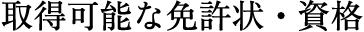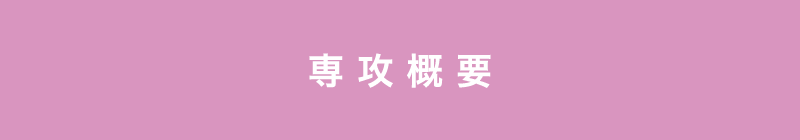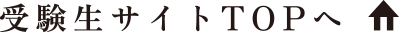- 2025年3月卒業生実績
-
就職決定率
-
職種・業種
-
主な就職先
- 【公立学校養護教諭】
- 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京都、奈良県、横浜市、川崎市
- 【私立学校養護教諭】
- 愛知県、千葉県
- 【児童指導員】
- 相和福祉協会、福祉の心、みらい福祉会、ドットライン
- 【公務員】
- 川崎市(行政職)
- 【その他】
- なごや福祉施設協会、SOMPOケア、キッザニア東京、ジェイアール東海高島屋、マイナビ、日本生命保険、日本調剤
- 2021年3月~
2024年3月卒業生実績 -
主な就職先
- 【公立学校養護教諭】
- 愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県、静岡県、浜松市、長野県、富山県、北海道、茨城県、埼玉県、群馬県、東京都、横浜市、川崎市、京都府、広島県・広島市、愛媛県
- 【私立学校養護教諭】
- 愛知県、名古屋市、三重県、静岡県、浜松市、東京都、京都府
- 【児童指導員・支援員】
- 公立学校(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)、ニューズ、みらい学びクリエイト
- 【公務員(行政職)】
- 知多市役所、豊橋市役所
- 【教育関係職員】
- 学校法人藤田学園、学校法人越原学園
- 【医療機関・団体・一般企業など】
- 半田市医師会健康管理センター、あいち知多農業協同組合、愛知PFS協会、野村不動産ライフ&スポーツ、名進研ホールディングス、日能研東海、名古屋教育文化センター、さなる、第一生命保険、トーエネック、オザワ科学、J-netレンタリース、中北薬品、スギ薬局
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
4年間で特に力を入れたのは、授業の内容や進め方次第で子どもたちが自分の健康に興味を持つきっかけをつくれる「保健科教育法」の授業です。小学生向けの模擬授業では、一目で理解できるような教具の制作を心掛け、中高生向けの模擬授業では、まず導入部分で興味を引くよう構成を練りました。3年次の「養護実習」では、小学校4年生を対象に思春期の体の変化というデリケートな内容で授業を行いましたが、児童から「大人になるのが楽しみになった」と言ってもらえて大きな自信に。模擬授業での学びが実習の成果に結びついたと感じています。卒業後は救急処置や保健管理など、実践的に学んだスキルを活かし、学校全体で子どもたちを守れる環境をつくりたいと思います。
※掲載内容は在学時に取材した
2025年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
養護教諭を養成するための実践的なカリキュラムと充実した施設環境で、同じ夢をもつ仲間たちと切磋琢磨した4年間。「保健科教育法Ⅰ」の授業では、対象学年や発達段階など、一人ひとりの特性に合わせた指導案を立てて模擬授業を行うことで、養護教諭に必要なスキルや知識が身につきました。「養護実習」で歯磨き指導をした際もこの学びを活かし、イラストをたくさん使ったスライドや歯の模型、歯ブラシをつくって児童に興味を持ってもらえるように工夫。対象学年に合わせた授業内容を考えて実践していた経験が、実習の成功につながりました。卒業後は児童・生徒一人ひとりと丁寧に向き合い、「子どもの成長を促せる保健室」をつくっていきたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2024年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる特に印象深かった授業は「健康相談の理論と方法」です。子どもの心理を学びながら、目線の合わせ方、会話の間の取り方など、カウンセリングの知識と技術を習得できました。3年次の「養護実習」では、クラスに馴染めなくなった児童に対応する機会がありました。「助けを求めたいけど今は何も話したくない」という葛藤が読み取れたので、カウンセリングのスキルを活かし、あえて話しかけたり、聞いたりせずに待っていたところ、徐々に悩みを打ち明けてくれるように。子どもの様子から心理状態を理解し、それに合わせたケアを実践できたことで、自信を持って採用試験に臨むことができました。これからも子どもの心身の様子をしっかりと見つめ、信頼される養護教諭をめざします。
※掲載内容は在学時に取材した
2023年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
学内では養護教諭に必要な知識とスキルを学び、学外では実習を通して広い視野と実践力を養いました。2年次の「臨床実習」では小児科のある病院へ。複数の医療従事者で治療方針を検討するカンファレンスを見学し、学校内でも他の先生方と情報共有することが大切だと感じました。また3年次の「養護実習」では、小学校1年生を対象にしたプライベートゾーンに関する保健指導を実践。学年に合わせて視覚で伝わるようTVモニターやイラストを活用し「こう言われたらどう思う?」と問いかけながら伝えることで、理解につながりました。卒業後は保健室の外でも子どもたちとのコミュニケーションを大切にし、悩みに寄り添い、安心感を与えられる養護教諭になりたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2025年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
私は元々控えめな方でしたが、演習やゼミなどで討論を重ねていくうちに養護教諭が果たすべき役割の大きさを実感。子どもの安全・健康を守るため、積極的に発言・行動する力を身につけました。4年次の「保健科教育法Ⅳ」ではICTを使って授業を組み立てる方法を学び、習得した内容を「教育実習」で実践。生徒同士の話し合いやロールプレイングも交えながら場面に応じて効果的にタブレット端末を活用することで、わかりやすい授業をつくることができました。これから働く学校も、英語教育やICTに力を入れている小学校。大学で学んだことを活かし、学校保健のスペシャリストとして、児童や先生方から信頼される養護教諭になりたいと思います。
※掲載内容は在学時に取材した
2024年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる4年間の学びを通じて、ケガや病気への対応力だけでなく、子どもを指導するスキルの習得にも力を注ぎました。きっかけとなったのは「健康相談演習」や「教育相談とカウンセリング」などの授業で、子どもを受容し共感しながら、成長へと導くことも養護教諭の役割だと学んだことです。その後は教職課程で取り組んだ模擬授業を通して指導力を磨き、ゼミナールで健康課題をテーマに仲間とディスカッションを繰り返すことで、要点をわかりやすく伝える力を養いました。卒業後は、子どもたちとの日々のコミュニケーションを通して健康に関する課題を見つけ、養護教諭だからこそできる教育と指導をしていきたいと思います。
※掲載内容は在学時に取材した
2023年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
養護教諭である私の仕事は、毎朝子どもたちを迎えることから始まります。表情や様子がいつもと違う子どもには声を掛け、早期対応につなげています。その後も水質検査や各クラスから集めた健康観察情報の集計、保健だよりの作成、保健教育などの職務を行い、保健室への来室があれば随時ケアにあたります。ケガの場合、状況や程度を確認することはもちろん、安心して手当てを受けられるように、「痛かったね」と子どもの気持ちに寄り添うことも重視しています。体調がよくない場合は、体温や脈拍などのバイタルサインを測ります。頭痛や腹痛の背景には悩みや生活習慣の乱れが隠れていることもあるので、丁寧に話を聞き取り、必要に応じて継続的に支援したり、担任の先生に相談したりします。そしてケガでも病気でも状態が深刻でない場合は、頑張って教室に戻るか、保健室で休むか、子ども自身に判断を委ねます。保健室でのかかわりを通して、自分自身で考え、言葉にして伝える力を身につけてほしいと考えています。

高校時代にお世話になった養護教諭に憧れ、その方の母校でもある名古屋学芸大学に入学しました。養護教諭の養成を主とした専攻だけに、授業の内容は現場に直結するものばかり。アセスメントやさまざまな疾病の応急処置法、カウンセリング技法、発達段階に応じた保健指導のスキルなど、当時学んだことすべてが役に立っています。なかでも印象的なのは、スクールソーシャルワーカーの先生の授業で、「自立している人=SOSを出せる人」と教わったこと。一人で何でもこなせる力ではなく、助け合いながら生きていく力が大切なのだと驚きました。その気づきから、子どもに何もかもをやってあげるのではなく、まずは主体的に考えさせて、必要な時は助けを求められるようにサポートしたいという養護教諭観が定まりました。ケガや病気から回復し、子どもたちが元気になった姿を見せに来てくれるのは、何よりうれしい瞬間です。今後も他の先生や保護者、学校医など周囲の方々と協力しながら、子どもの心身の成長を見守っていきたいです。

※掲載内容は2025年2月現在の情報です。
閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる児童数約600人の公立小学校で養護教諭をしています。健康教育や職員会議、欠席者などの集計、保健だよりや掲示物の制作、日報や各種書類の作成など、職務は多岐に渡りますが、私が最も重視しているのは保健室での対応です。病気やケガの処置はもちろんですが、体調の悪くない児童も、処置以外の時間なら来室しておしゃべりできるルールにしています。何気ない会話や表情から、家庭や友人関係などのトラブルに気づけることも多く、必要に応じて担任の先生や保護者、スクールカウンセラーなどと連携しながら、その中心となって最適な支援を考え、実践します。上手くいかないこともありますが、児童が私を信頼し、悩みを話してくれたり、問題が解決した児童が明るい表情を見せてくれたりするのは何よりうれしく、この仕事を選んで良かったと感じます。今後も、一人ひとりの心とからだの安全と健康を守りながら、これから先に起こるであろう困難やストレスに負けない力を育んでいきたいです。

小学生の頃、いつも笑顔で話を聞いてくれる養護教諭や保健室の雰囲気が好きで、憧れるようになりました。高校生になって進路を考える時も、養護教諭になりたい気持ちは変わらず、養護教諭の採用者数が中部地区でトップクラスの名古屋学芸大学なら、より高い確率で夢を実現できるのではと思い、入学しました。授業では、救急処置やカウンセリング、健康教育の技法など、養護教諭に必要な幅広い知識とスキルを学びました。どの授業も実践的で、具体的なケースや対象者が設定され、個人やチームでアプローチの方法を考え、実践し、考察するスタイル。さらに学内の「子どもケアセンター」で、託児ボランティアに取り組めたことで、知識だけでなく臨機応変な対応力も身につきました。小学校への入職1年目からさまざまな職務を全うできたのも、こうした幅広い経験のおかげです。また、クラス全員で養護教諭をめざし、切磋琢磨しながら学べる環境も学芸ならではのポイントです。先生方や仲間たちには本当に感謝しています。

※掲載内容は2023年1月現在の情報です。
閉じる
- 養護教諭一種
- 中学校教諭一種(保健)
- 高等学校教諭一種(保健)
- 健康管理士一般指導員
- 学校心理士認定運営機構 准学校心理士
- 社会福祉主事(任用資格)

就職活動やキャリア形成に役立つ各種資格の取得を奨励するため、対象となる60種類以上の資格において、
取得(合格)した資格の受験料全額を支給します。在学中に1人4回まで利用できます。
- 子どもケア専攻<養護教諭>に
関連する対象資格の一例 -
- 健康管理士一般指導員
- 心理学検定
- 幼児体育指導者
- 認定ベビーシッター