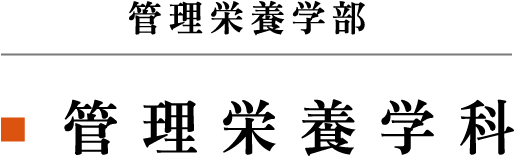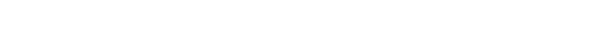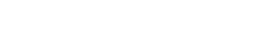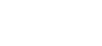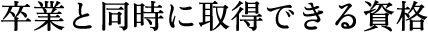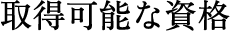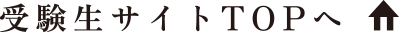- 2025年3月卒業生実績
-
就職決定率
-
業種
-
主な就職先
- 医療機関(管理栄養士)
-
- 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
- 伊勢赤十字病院
- JA愛知厚生連 安城更生病院
- JA岐阜厚生連
- 豊橋市民病院
- 春日井市民病院
- 小牧市民病院
- 豊川市民病院
- 大垣市民病院
- 藤枝市立総合病院
- 岐阜県総合医療センター
- 浜松医療センター
- 愛知県医療療育総合センター
- 藤田医科大学病院
- 刈谷豊田総合病院
- 名古屋掖済会病院
- 中部国際医療センター
- 八千代病院
- 松波総合病院
- 半田市医師会健康管理センター など
- 福祉施設(管理栄養士)
-
- 社会福祉法人紫水会
- 社会福祉法人福寿園
- 社会福祉法人聖隷福祉事業団
- 社会福祉法人青大悲福祉協会 など
- 行政機関
-
- 三重県(管理栄養士)
- 知立市(管理栄養士)
- 八百津町(管理栄養士)
- 厚生労働省(食品衛生監視員)
- 名古屋市(食品衛生監視員) など
- 教育機関(栄養教諭)
-
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 浜松市
- 給食(管理栄養士)
-
- 日清医療食品
- エームサービス
- グリーンハウス
- LEOC
- 日本ゼネラルフード など
- 食品(品質管理職・生産技術職・総合職など)
-
- ニップン
- 日本食研ホールディングス
- 名古屋製酪
- 井村屋グループ
- マルコメ
- わらべや日洋食品
- 壱番屋
- シノブフーズ
- ロック・フィールド
- 中部フーズ
- 太陽油脂
- 大東カカオ など
- ドラッグストア・調剤薬局(管理栄養士・総合職など)
-
- ウエルシア薬局
- ツルハ
- スギ薬局
- 杏林堂薬局
- アインホールディングス
- マツモトキヨシ など
- その他(総合職など)
-
- 豊橋農業協同組合
- 中北薬品
- 良品計画
- オークワ
- フジマック など
- 2021年3月~
2024年3月卒業生実績 -
主な就職先
- 医療機関(管理栄養士)
-
- 地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター
- 地域医療機能推進機構(東海北陸地区)
- JA愛知厚生連(江南厚生病院・渥美病院・豊田厚生病院・海南病院・安城更生病院・足助病院)
- JA岐阜厚生連
- JA三重厚生連
- JA静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院
- 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
- 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
- 日本赤十字社岐阜赤十字病院
- 高山赤十字病院
- 小牧市民病院
- 津島市民病院
- 蒲郡市民病院
- 一宮市立市民病院
- 半田市立半田病院
- 大垣市民病院
- 岐阜県立多治見病院
- 藤枝市立総合病院
- 浜松医療センター
- 富士市立中央病院
- 市立敦賀病院
- 公立松任石川中央病院
- 愛知医科大学病院
- 藤田医科大学病院
- 藤田医科大学ばんたね病院
- 藤田医科大学七栗記念病院
- 岐阜大学医学部付属病院
- 静岡済生会総合病院
- 三郷中央総合病院
- 社会医療法人大雄会 大雄会第一病院
- 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院
- 名鉄病院
- 中部国際医療センター
- 総合病院 聖隷浜松病院
- 恵寿総合病院
- 刈谷豊田総合病院
- 医療法人名南会 名南病院
- 医療法人社団誠道会 各務原リハビリテーション病院
- 医療法人社団恵成会 豊田えいせい病院グループ など
- 福祉施設(管理栄養士)
-
- 社会福祉法人愛知県厚生事業団
- 社会福祉法人紫水会
- 社会福祉法人なごや福祉施設協会
- 社会福祉法人西春日井福祉会
- 社会福祉法人恒心福祉会
- 医療法人清水会
- 社会医療法人大雄会
- 社会福祉法人相和福祉会
- 社会福祉法人福寿園
- 社会福祉法人觀寿々会 など
- 行政機関
-
- 厚生労働省(食品衛生監視員)
- 名古屋市(食品衛生監視員)
- 名古屋市(管理栄養士)
- 愛西市(管理栄養士)
- 大垣市(管理栄養士)
- 中津川市(管理栄養士)
- 飯田市(管理栄養士)
- 豊田市(行政職)
- 多治見市(行政職) など
- 教育機関
-
- 愛知県(栄養教諭)
- 名古屋市(栄養教諭)
- 岐阜県(栄養教諭)
- 広島県(栄養教諭)
- 静岡県(栄養教諭)
- 浜松市(学校栄養職員) など
- 給食(管理栄養士)
-
- 日清医療食品
- シダックス
- エームサービス
- グリーンハウス
- LEOC
- 日本ゼネラルフード
- 富士産業
- 魚国総本社
- ナリコマエンタープライズ
- グランドスポーツ など
- 食品(品質管理職・生産技術職・総合職など)
-
- 明治フレッシュネットワーク
- マルサンアイ
- 山崎製パン
- フジパングループ本社
- 日本食研ホールディングス
- 井村屋
- 極洋
- わらべや日洋食品
- 伊那食品工業
- 杉本食肉産業
- ユーハイム
- 有楽製菓
- 名古屋製酪
- ヤタロー
- 日本ルナ
- エバラ食品工業 など
- ドラッグストア・調剤薬局(管理栄養士・総合職など)
-
- 杏林堂薬局
- スギ薬局
- 中部薬品
- マツモトキヨシ
- アインホールディングス
- アインファーマシーズ
- たんぽぽ薬局
- サンドラッグ
- ゲンキー
- クスリのアオキ
- ウエルシア薬局
- スギヤマ薬品
- コスモス薬品
- キョーワ薬局 など
- その他(総合職など)
-
- イオンリテール
- ユニー
- 生活協同組合コープあいち
- 中北薬品
- フィールコーポレーション
- 物語コーポレーション
- ゼンショーホールディングス
- 成城石井
- コロワイドMD など
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
2年次の「臨床栄養学」の授業で、食事がさまざまな病気の治療に深くかかわっていることを知り、専門的に学びたいと思うようになりました。ゼミナールでは臨床栄養学研究室に所属し、病院で患者さんのデータや様子を確認しながら経過をまとめるなど、実践的な研究に取り組みました。またスポーツ栄養の知識を活かして活動するサークル「NSTA」では、他大学の運動部員を栄養面からサポートし、アスリートの努力や実績に貢献できることにやりがいを感じました。こうした経験を活かし、卒業後は患者さんの病態や好みに合わせた食事を提供することに加え、現場で得た知見を広く医療に役立てるため、研究活動にも力を注ぎたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2025年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
3年次に受けた「公衆衛生学実習」がきっかけで、自治体の管理栄養士をめざすようになりました。授業では、三重県津市の中高年の健康課題を題材として、野菜摂取を促すプランを立案。地域住民の健康課題をデータから読み解き、解決策を提案する経験を通じて、「治療より予防」という考え方に興味を持ちました。また、「応用栄養学」の授業では、幼児から高齢者まで各ライフステージに必要な栄養素を学び、病気の予防のために「食」の知識を活かせると実感しました。卒業後は三重県内の保健所に勤務し、給食施設での栄養管理や、県民の皆さんを対象とした健康教育、飲食店へのヘルシーメニュー提供の働きかけなどにも携わりたいと思っています。
※掲載内容は在学時に取材した
2025年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる病院への就職をめざし、医療領域の学びに強い名古屋学芸大学の管理栄養学科に入学しました。講義で基礎的な知識を学んだ後、実習で具体的な症例の栄養ケアプランを作成する「臨床栄養学」など、授業はどれも実践的。回を重ねるごとに多様な症例に関する知識が身につき、その後の病院実習でも実際の患者さんに対するケアプランの計画に参加することができました。また在学中、サークル「NSTA」で近隣大学のバレーボール部の学生の食事をサポートできたことも、かけがえのない経験です。大学で培った実践力とコミュニケーションスキルを活かし、就職後は、患者さん一人ひとりに寄り添い、心身ともに元気にできる管理栄養士をめざします。
※掲載内容は在学時に取材した
2024年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
管理栄養学科の幅広い学びを通して私が強く感じたのは、「食はすべての人の基盤」ということ。病気の有無や年齢にかかわらず、あらゆる人の役に立ちたいと考え、食品メーカーへの就職を志望しました。3年次からは、食生態学のゼミナールで食育について研究を深めながら、食品メーカーのインターンシップにも参加。なかでも内定先のマルサンアイは、スーパーや病院、給食会社など幅広い取引先向けに、健康的な大豆製品を開発・提供していることに魅力を感じました。入社後は、製品とともに、病態に合わせた献立や誰でも簡単にできる調理法の提案、食育イベントの企画などに取り組み、多くの人々に「食べる楽しさと健康」を届けていきたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2024年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる栄養教諭をめざし、授業で専門知識とスキルを深めながら、さまざまな小学校でボランティア活動を行うことで、子どもたちと触れ合いました。その際、自治体ごとに異なる給食システムや、食育の方針、教育理念を知り、栄養教育に最も共感した名古屋市の栄養教諭をめざすことにしました。進路を考える中で、「子どもたちに求められる栄養教諭になれるかな」と不安に思う時期もありましたが、お世話になった先生から「もっと自分を出していけば大丈夫」と背中を押してもらえたおかげで、自信を持って採用試験に臨め、合格することができました。卒業後は、大人になっても大切にし続けられる、正しい食習慣や栄養の知識を子どもたちに伝えていきたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2023年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
高校時代から栄養教諭に興味があり、栄養教育の学びが充実している名古屋学芸大学に入学しました。教職科目の「栄養教育実習指導」では模擬授業に取り組み、わかりやすい授業構成や伝え方を徹底的に鍛えました。中学校での教育実習では、カルシウムの働きをゲーム形式で学ぶ授業を行い、授業後に生徒が「これからは野菜も意識して食べるよ」と言ってくれて自信がつきました。ゼミナールで子どもたちの食への意識を調査したり、課外活動として福島県南相馬市の地域活性化のために地元の食材を使ったレシピを考案して提供したり、食を通して多くの人と交流できたのも貴重な経験です。卒業後は、栄養教諭として地域の食文化も含めた食の魅力、そして食べることの楽しさや大切さを伝えていきたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2025年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
3年次の「応用栄養学実習」で、高齢者やスポーツ選手など、毎回異なる対象を設定し、必要な栄養素や食べやすさを考慮した献立作成・調理に取り組みました。またサークル「Canteen」の活動では、大学のある日進市の施設やイベントで販売するランチ、スイーツの開発にも挑戦。栄養価の計算や見た目の美しさはもちろん、衛生管理やコスト管理の実践力も身につきました。こうした経験から食品会社の開発職をめざすように。内定をいただいた井村屋は、アイスなど多くの商品を手掛けていること、また、アスリートのエネルギー補給にも適した商品を手掛けている点にも魅力を感じ、志望しました。将来的に、多くの人々の需要に応える商品の開発に取り組みたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2025年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
健康と栄養について知識を深めるうちに、将来は病気の予防に携わりたいと考えるようになりました。なかでも地域住民の栄養改善や健康増進を広くサポートする行政機関の仕事に魅力を感じ、卒業後の進路に選びました。2年次の「栄養カウンセリング演習」では、地域住民を想定した栄養指導を実践。栄養と健康の重要性をわかりやすい言葉で伝えるスキルを身につけました。また、保健所での「管理栄養士実習」では、栄養指導や各施設の巡回、健康調査など多岐にわたる業務を間近で見学し、自分が働く姿をイメージすることができました。卒業後は名古屋市の管理栄養士として、丁寧な栄養指導を行うなど、市民の健康のために力を発揮したいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2024年2月末現在の情報です。閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる家族が病気をした時の経験から、病気を患う人の食と栄養を支える管理栄養士をめざしました。名古屋学芸大学は医療領域の学びが充実していて、「臨床栄養学実習」では多様な症例に合わせた献立作成や嚥下(えんげ)食の調理法を、「臨床医学演習」では病院で働く管理栄養士からさまざまな症例の検討や病院での取り組みを学び、現場で活かせる実践的な知識を吸収しました。また「臨地実習」では、医師や看護師らと連携して患者さんの栄養管理を行うNST(栄養サポートチーム)の業務に参加し、医療現場での管理栄養士の役割の大きさを改めて実感しました。大学での学びを糧に、卒業後は急性期医療を担う病院でチーム医療に取り組み、患者さんをサポートしていきたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2023年2月末現在の情報です。閉じる
-
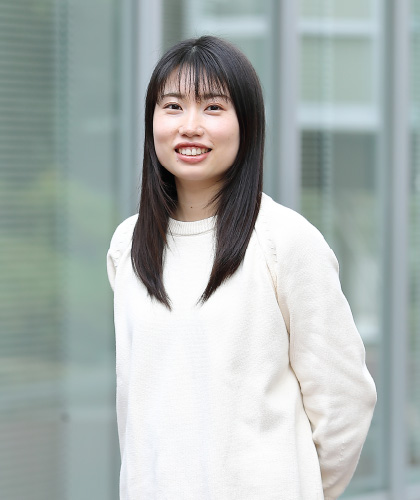
詳しく見る
詳しく見る閉じる私の祖父は糖尿病を患っていて、食事制限に苦労している様子を間近で見ていました。そうした経験から、病気になる前の一次予防に広く携わることができる、行政機関で働く管理栄養士をめざそうと決めました。2年次の「応用栄養学」で、離乳食や子ども向けの食育について学んだことで、幼少期に正しい食習慣を身につけることの大切さを実感。その後はゼミナールでの食物アレルギーの研究と並行して、「地域コミュニケーション論」で円滑な意見交換の仕方や効果的な伝え方を、さらに市役所での実習で、市民と協力して栄養のイベントを企画・運営する、行政機関での実務を学びました。卒業後は、子どもから大人まで市民が気軽に相談できる管理栄養士になれるよう努めたいです。
※掲載内容は在学時に取材した
2023年2月末現在の情報です。閉じる
-
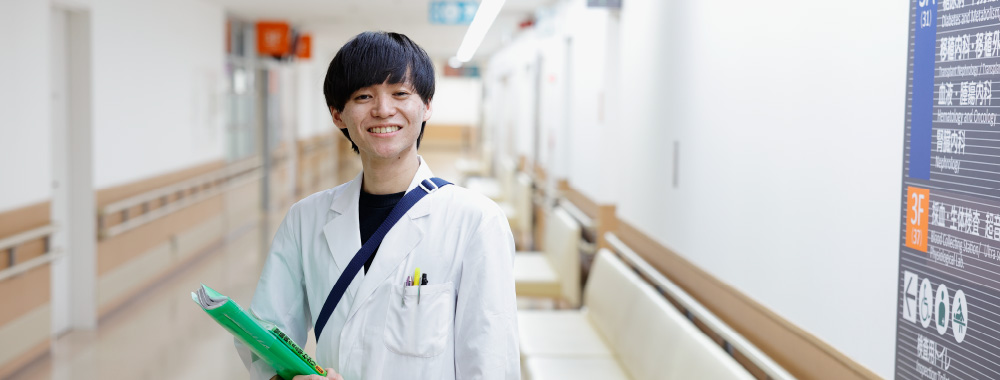
詳しく見る
詳しく見る閉じる名古屋の高度医療・急性期医療の中核を担う日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院の管理栄養士として、患者さんへの栄養指導と、NST(Nutrition Support Team:栄養サポートチーム)業務を担当しています。患者さんの病態や年齢、生活スタイルはさまざまですから、栄養指導では、対話を通じて患者さんを理解することが第一歩。例えば「塩分制限が必要だけどインスタント食品が大好き」という方には、いきなり禁止するのではなく、徐々に量を減らしつつ、その他の食事で減塩する方法を伝えるなど、「それならできるかも」と思ってもらえるように心掛けています。またNST の業務では、週1 回、医師や看護師らと行うカンファレンスに参加し、栄養状態の良くない患者さんの食事の方針を検討します。その際も必要があれば患者さんのベッドサイドに赴いて話を聞き、好きな食材や好み、状態に合う栄養補助食品を献立に取り入れるなど工夫します。栄養状態が改善し、患者さんが元気になっていくのを間近で見られるのが、何よりのやりがいです。

興味のあった食と栄養の知識で人の役に立ちたいと思い、名古屋学芸大学に入学しました。大学の学びは幅広く、医療現場に直結した知識を身につける臨床栄養や人体、疾病に関する授業はもちろん、食中毒菌の実験や、環境衛生についての学習にも励みました。また、「食品学」の授業では、食品成分や健康食品についての知識を習得。抗酸化作用のあるビタミンC や代謝を促進するビタミンB1のように治療や健康維持には欠かせないものなど、数多くの栄養素について学びました。在学中に臨床栄養の分野だけでなく、日常の食生活やスポーツ栄養など幅広い側面から学んだおかげで、実際の医療現場でも「治療のための栄養指導」という枠にとらわれず、患者さんの健康維持や生活習慣などあらゆる視点から考えて指導に取り組めています。今後の目標は、「この病態なら任せてください」と自信を持って一人ひとりの患者さんを支援できる、より専門性の高い管理栄養士へと成長すること。そのために知見やデータを集め、学会にも積極的に参加するなど、研鑽を続けていきたいです。

※掲載内容は2022年11月現在の情報です。
閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
調味料をはじめとする幅広い商品の製造・販売を行う日本食研で、業務用の焼肉のたれや唐揚げ粉などの開発を担当しています。例えばスーパーの焼肉弁当の場合、たれに漬け込んだ肉があらかじめ焼かれた状態で売られていますが、それを購入した消費者が自宅のレンジで加熱してから食べる、ということも少なくありません。こうした製造から食事に至るまでの過程を理解したうえで、最終的に香ばしさや味わい、食感、見た目がベストな状態になるように、食材や調味料、添加物の種類とバランス、配合する順序や加熱する時間などを変えながら試作を繰り返します。もちろん、ターゲットの性別や年齢層などに合わせて味の濃淡や風味も細かく調節しています。ただ自分が美味しいと思うものをつくるのではなく、消費者の口に届くまでの過程やニーズを調査し、安全性やコスト、技術的な制約をクリアしながら美味しさを見極め、つくり上げていくのがこの仕事の面白さであり、難しさでもあります。

研究開発の仕事に興味を持ったのは、大学で食と人のかかわりを深く学んだことがきっかけでした。例えば「食品学」では、タンパク質の構造や、食塩、砂糖が食品に与える影響などを学び、食材をより美味しく食べるための方法を科学的に理解するとともに、味をつくる楽しさに出会いました。また、スポーツ栄養にも興味があり、近隣大学の運動部員の栄養管理を行うサークル「NSTA」に所属し、毎日朝晩の食事の献立作成から調理、提供までを行いました。自分の知識やスキルで人に喜んでもらえることにやりがいを感じ、もっと多くの人の役に立ちたいと思い、味そのものを広く扱えるこの仕事を選びました。仕事には大学の学びすべてが役立っていますが、特に「食品学」や「生化学」、ゼミナールで研究したアレルギーの知識、大量調理にも対応できるスキルは、管理栄養学科出身者ならではの強みであり、「人」を軸に商品を開発するうえで、なくてはならない要素となっています。

※掲載内容は2024年2月現在の情報です。
閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる
岐阜市の保健所で管理栄養士/食品衛生監視員として勤務しています。食品衛生課では飲食店の営業許可・更新や、食の安全に関する啓発活動、食品表示の適正化など幅広い業務を行っており、私は主に食品の収去検査と食中毒への対応を担当しています。食品の収去検査とは、製造・加工または流通する食品等について検査を実施し、安全性の確認および不良食品等の排除を行う仕事です。この際に食品が適切な温度で管理されているか、包装容器に記載された成分表示が正しいかなども確認し、必要に応じて指導を行っています。また、食中毒への対応業務では、食中毒が発生した際に患者さんに対する疫学調査を行います。施設に対しては、食中毒の再発防止を目的として、原因食品の調査および改善指導を行います。どちらの仕事も大学で学んだ細菌の種類や増殖する条件、厨房の衛生管理といった知識が求められ、高い専門性を発揮できる点にやりがいを感じています。

大学時代は病院への就職も視野に入れていたので、特に医療分野の科目に力を入れました。「臨床栄養」の授業では、病態に合わせた栄養指導の方法を学び、病気の予防と治療の両方に食事が大きくかかわっていることを、患者さんや一般の市民に向けてわかりやすく伝えるスキルを磨きました。また、「給食管理」の授業では病院や学校の大量調理をテーマに取り上げ、具体的な調理方法だけでなく、食中毒の発生要因や衛生管理についても知識を深めました。入職直後は健康増進課で市民向けの栄養指導を行っていましたが、食と栄養の知識があったからこそ説得力のある指導ができたと思います。また、現在の職場でも飲食店や小売店に対し、医療や健康の視点から食の安全性を説いています。管理栄養士や食品衛生監視員の資格を持って自治体で働く魅力は、保健所や病院、学校、保育施設など、配属先で異なるさまざまな仕事が経験できることです。これからも多彩なフィールドで大学で身につけた管理栄養士としての知識とスキルを発揮していきたいです。

※掲載内容は2024年1月現在の情報です。
閉じる
-

詳しく見る
詳しく見る閉じる栄養教諭の大きな職務のひとつは食育の推進。どう進めるかはそれぞれの栄養教諭に任される部分が大きく、私は「子どもたちが楽しめる食育」を心掛けて授業や活動に取り組んでいます。例えば、1年生のクラスで始めた「お味見当番」。給食の前に当番の子どもが味見をし、食材や栄養についての説明や、食べた感想を発表することで、食への興味や理解を深めます。また各学年の学級活動の時間を利用した授業では、給食をつくってくださっている調理員の仕事に密着した動画をつくって紹介し、感謝の気持ちを育みました。こうした企画や教材の制作はもちろん、日々の授業や学校生活の中に食育の時間を取ってもらえるよう、担任や教科の先生方に働きかけるのも栄養教諭の仕事です。授業で身につけた知識を通して、子どもたちが好き嫌いを克服したり、食事を楽しむようになったりと、頑張った分だけ子どもたちが成長してくれるのが毎日のエネルギーです。私が伝えた栄養の知識や食習慣が、子どもたちの現在だけでなく、生涯の健康を支える。そんな気概を持って、試行錯誤しながら栄養教諭の仕事に取り組んでいます。

食育以外にも、献立作成や給食管理、アレルギー対応など、栄養教諭の仕事は多岐にわたりますが、大学での学びがあったからこそ、幅広い業務にも楽しみながら取り組めています。大学では、今の職務にも直結する多様な授業で実践力が鍛えられたのはもちろん、海外研修や、震災の被災地で食事を提供するボランティア活動、ゼミナールでの企業との共同研究などを通して、人と人のこころや文化をつなぎ、広く社会の健康を支える“食”の役割の大きさを体感しました。「何でも挑戦して楽しむ」。そんな風土が学科全体に根付いていて、日々の授業やサークル活動はもちろん、採用試験や国家試験前でさえ、勉強後にみんなでご褒美ごはんをつくって労い合うなど、楽しみながら乗り切ったのもいい思い出です。培った気質は栄養教諭になった今も健在。食育の研究会に所属するほか、食育推進のキャラクターと紙芝居を考案し、名古屋市の食育教材として採用してもらうなど、栄養教諭の枠にとらわれず、さまざまな活動に取り組んでいます。今後も子どもたちのための食育に取り組み、一緒に成長していきたいです。

※掲載内容は2022年11月現在の情報です。
閉じる
- 管理栄養士(受験資格)
- 栄養士(取得資格)
- 食品衛生監視員(任用資格)
- 食品衛生管理者(任用資格)
※任用資格:企業・機関などが採用の条件とする場合があるが、管理栄養学科のカリキュラムを履修することで取得できる。
- 栄養教諭一種
- 健康運動実践指導者(受験資格)
- 健康食品管理士/食の安全管理士(受験資格)

就職活動やキャリア形成に役立つ各種資格の取得を奨励するため、対象となる60種類以上の資格において、
取得(合格)した資格の受験料全額を支給します。在学中に1人4回まで利用できます。
- 管理栄養学科に関連する
対象資格の一例 -
- 健康運動実践指導者
- 健康食品管理士/食の安全管理士
- 家庭料理技能検定