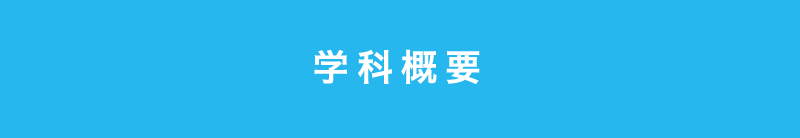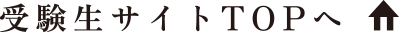憧れを抱きました。
母が病気で入院した時、私はただ心配で見守ることしかできませんでした。そんな中、担当の看護師さんが私にも優しく接してくださったことに感動し、この道をめざそうと決めました。名古屋学芸大学を選んだ理由は、隣接する名古屋医療センターで実習が受けられ、海外研修に参加できる点に魅力を感じたからです。


4年間の学びを進めるうえで、基礎となる知識や技術を幅広く身につけたのが1年次でした。例えば「基礎看護学実習」ではベッドメイキングの手順を習得し、「解剖生理学」では人体の構造と仕組みを理解。さらに「病態治療学」では名古屋医療センターの医師が教壇に立ち、具体的な疾患とその治療方法をわかりやすく解説していただきました。これらの学びを通して看護師は医療職であることを再認識するとともに、自信を持って患者さんに向き合う心構えができました。加えて防災人材育成プログラムに参加するなど、将来に活かせる講座を積極的に受講しました。



2年次からは、1年次に学んだ知識をベースにしながら、患者さんへの具体的な接し方や看護技術といった実践的な知識とスキルを身につけました。「ヘルスアセスメント」の授業では、対話(主観的情報)と検査結果(客観的情報)を基に、患者さんの状態をアセスメント(評価・分析)する方法を習得。また、「基礎看護学技術論」では注射や点滴の手法を学び、患者さんの前でも落ち着いて処置ができるようになるまで何度も練習を重ねました。これらの授業はグループワークで取り組むことが多く、看護師同士で連携する職場のロールプレイにもなり、チームワークも身につきました。



3年次はさまざまな看護学実習を経験し、医療現場の緊張感を肌で感じました。「急性期実習」で同じ疾患を抱えた二人の患者さんを担当した際には、病歴や年齢、生活スタイルによって、身体的、精神的苦痛が異なることを実感。ここで役立ったのが「成人看護学実践論」で学んだ病態関連図でした。日常生活やご家族との関係、疾患の原因などをマップ状に記していくもので、患者さんの現状を知り、今後の治療方針を把握するための材料となるものです。実習中はこれをもとに「手術後にどんな合併症が懸念されるか」「退院後はどんな生活を望んでいらっしゃるか」などを頭の中で整理しながら対応することができました。



4年間の学びの総まとめに位置づけられる「統合実習」で、実際の医療現場のように複数の患者さんを担当しました。患者さんの情報を医療チーム全体で共有するために客観的な視点から記録を残しつつ、異常があればすぐに察知できるよう、コミュニケーションをとりながら適切なケアをすることができました。講義では「キャリアデザイン」「国際看護学」などを受講し、ワークライフバランスと長期的なキャリアを明確化。結婚や出産といったライフステージが変化しても長く看護師を続けたいと考え、全国にネットワークを持つ国立病院機構 名古屋医療センターへの就職を決めました。
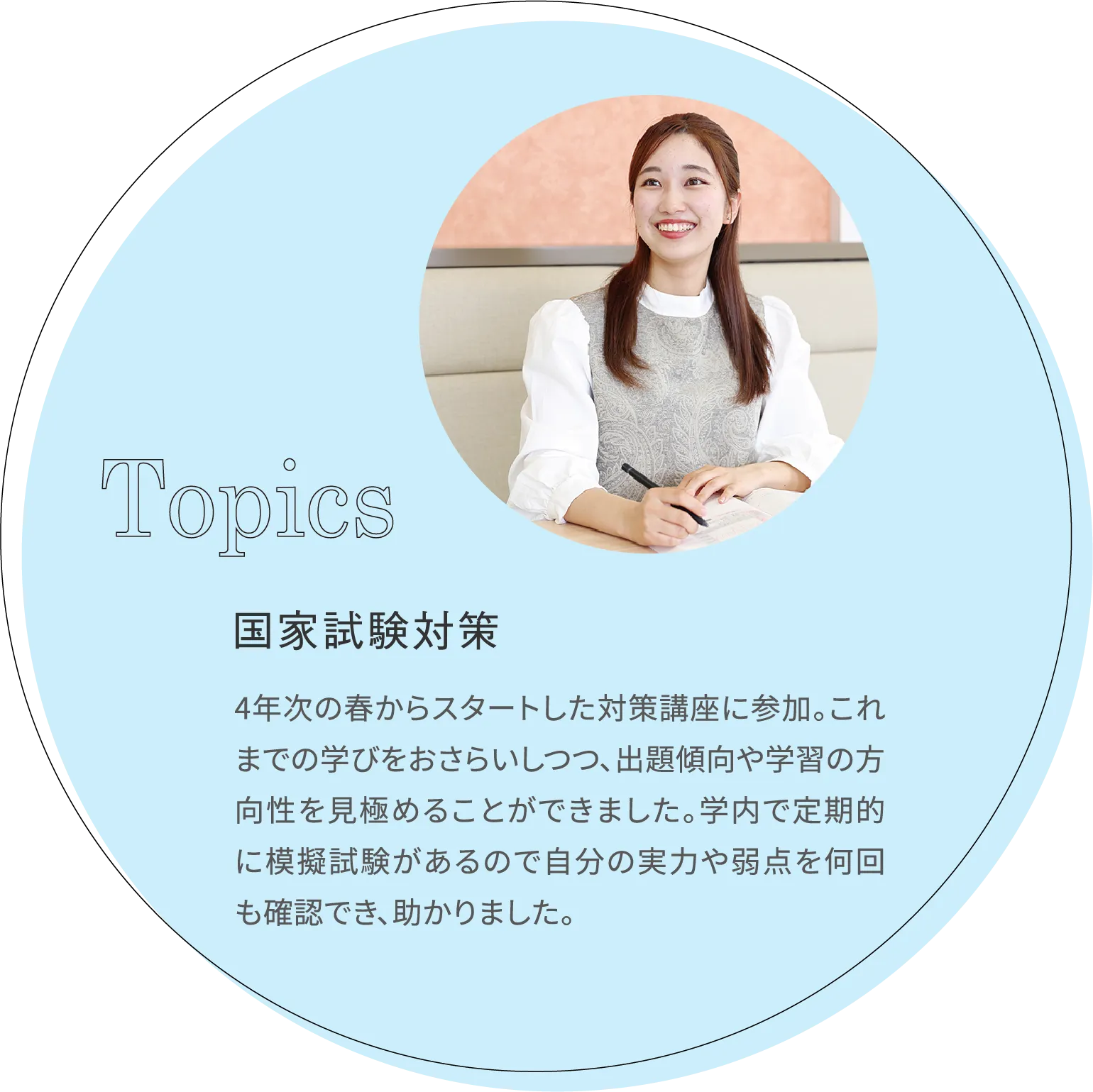
※掲載内容は在学時に取材した2024年2月末現在の情報です。
※2022年度入学生用のカリキュラムから内容が改定されているため、
現在のものとは開講時期や実施内容が異なる場合があります。





同じ道をめざしました。
祖母が名古屋医療センターに入院した時、患者さんをやさしく支える看護師を見て、私もいつか同じようになりたいと憧れて看護師を志すように。名古屋医療センターと連携した学びが展開されていて、演習・実習が充実している点と、立地が良く通学しやすい点に魅力を感じ、名古屋学芸大学に入学しました。


1年次は病態についての知識や、看護の技術を学び、看護師をめざすうえでの基礎を固めました。内容は専門的ですが、経験豊富な先生方にわかりやすく丁寧な指導をしていただきました。例えば、「解剖生理学1・2」では、先生が要点をまとめたノートをつくってくださり、複雑な人体の構造や機能を着実に理解することができました。また「基礎看護学技術論1・2」では、バイタルサインの測定やシーツ交換などの技術を習得。シーツの僅かな皺が、患者さんの床ずれにつながるなど、一つひとつの作業の大切さを学び、「基礎看護学実習1」では、実際に患者さんとのコミュニケーションを通して、医療現場での看護師の役割を肌で感じる機会になりました。



2年次になると、聴診や採血、酸素療法など、より高度な看護技術を演習・実習を通して身につけました。さらに小児や母性、精神などさまざまな領域に学びが広がり、多様な患者さんに対応するための知識を習得しました。後期に取り組んだ「基礎看護学実習2」では、麻痺があり、会話もできないがん患者さんを担当し、呼吸状態や清潔状態などのアセスメント(分析・評価)を行いました。反応がなくても毎日声を掛け続けると、アイコンタクトなどで意思疎通ができるようになり、1日1日の地道なケアが「患者さんの治療を支える」ことを実感しました。
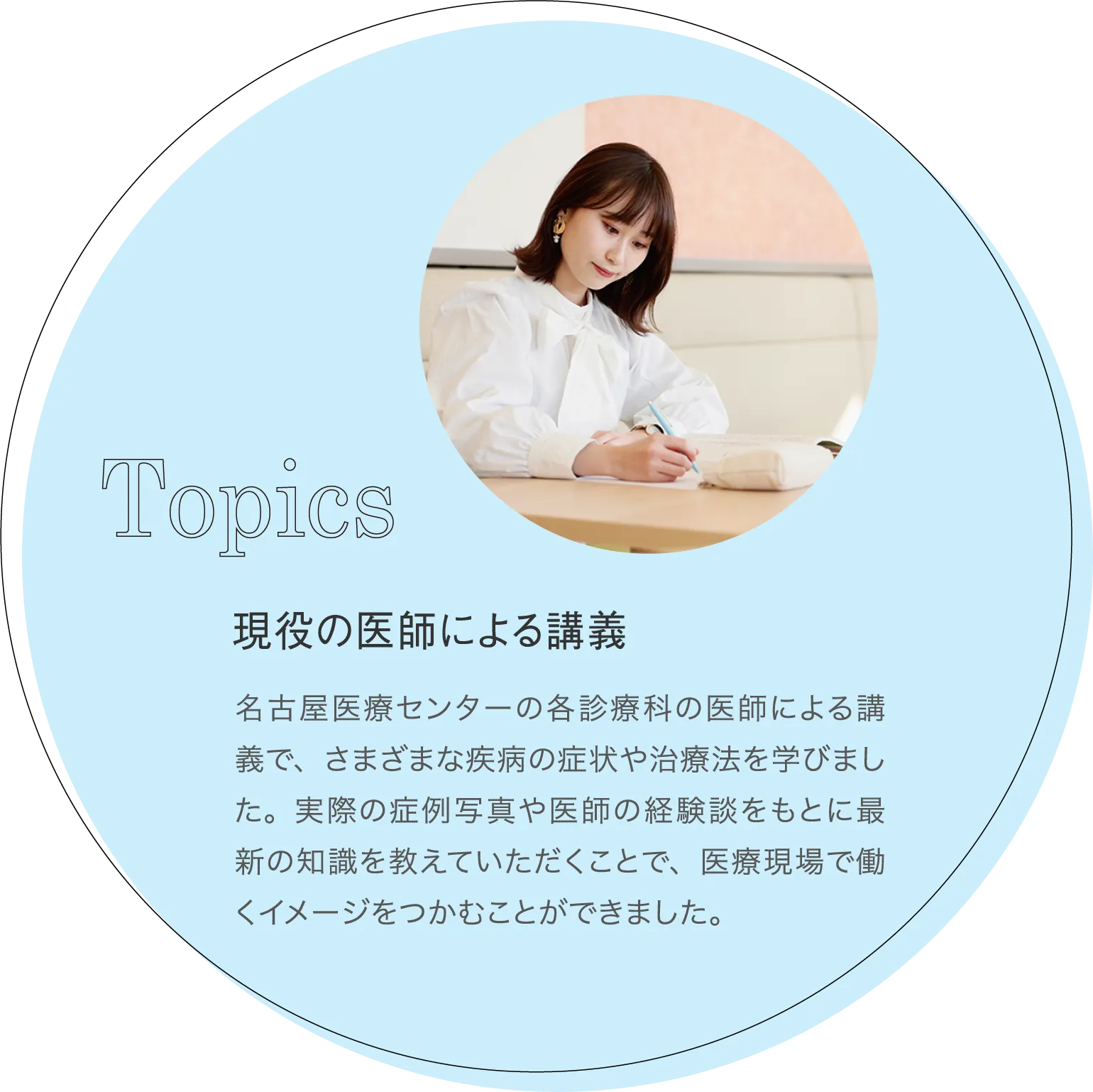


3年次は小児、母性、老年、精神、在宅看護学領域の幅広い実習に臨み、実践力を磨いた1年でした。患者さんのアセスメントを行いながら、診療科ごとの特徴や、それぞれの患者さんに適した看護のあり方を学びました。その中でも印象的だったのが「精神看護学実習」。病気の影響で何事にも関心がなく、治療への意欲を持てなかった患者さんと信頼関係を築き、最終的には社会復帰に向けてのリハビリをスタートすることができました。自分の働きかけが、患者さんの治療へのモチベーションになったことが自信になりました。また、看護学実習の多くは隣接する名古屋医療センターで行われ、同病院で勤務経験のある教員が同行してくださるので、難しい処置にも落ち着いて取り組めました。



4年間の集大成となる「統合実習」では、初めて複数の患者さんを担当するとともに、少ない人数の看護師で患者さんをケアする夜勤業務の一部も経験。それぞれに適したアセスメントに加え、効率的なケアの流れや時間配分を学びました。また、師長の業務に同行させてもらい、観察しながら学ぶ「シャドーイング」を行ったことで、現場での動き方をより高い視点から考えられるようになったのも収穫でした。その一方で、国家試験対策も本格化。国家試験対策講座は領域ごとに集中して行われ、学生がつまずきやすいポイントをわかりやすく学べました。クラスメイトとも問題を出し合うなど、みんなで支え合えたおかげで、最後まで頑張り続けることができました。
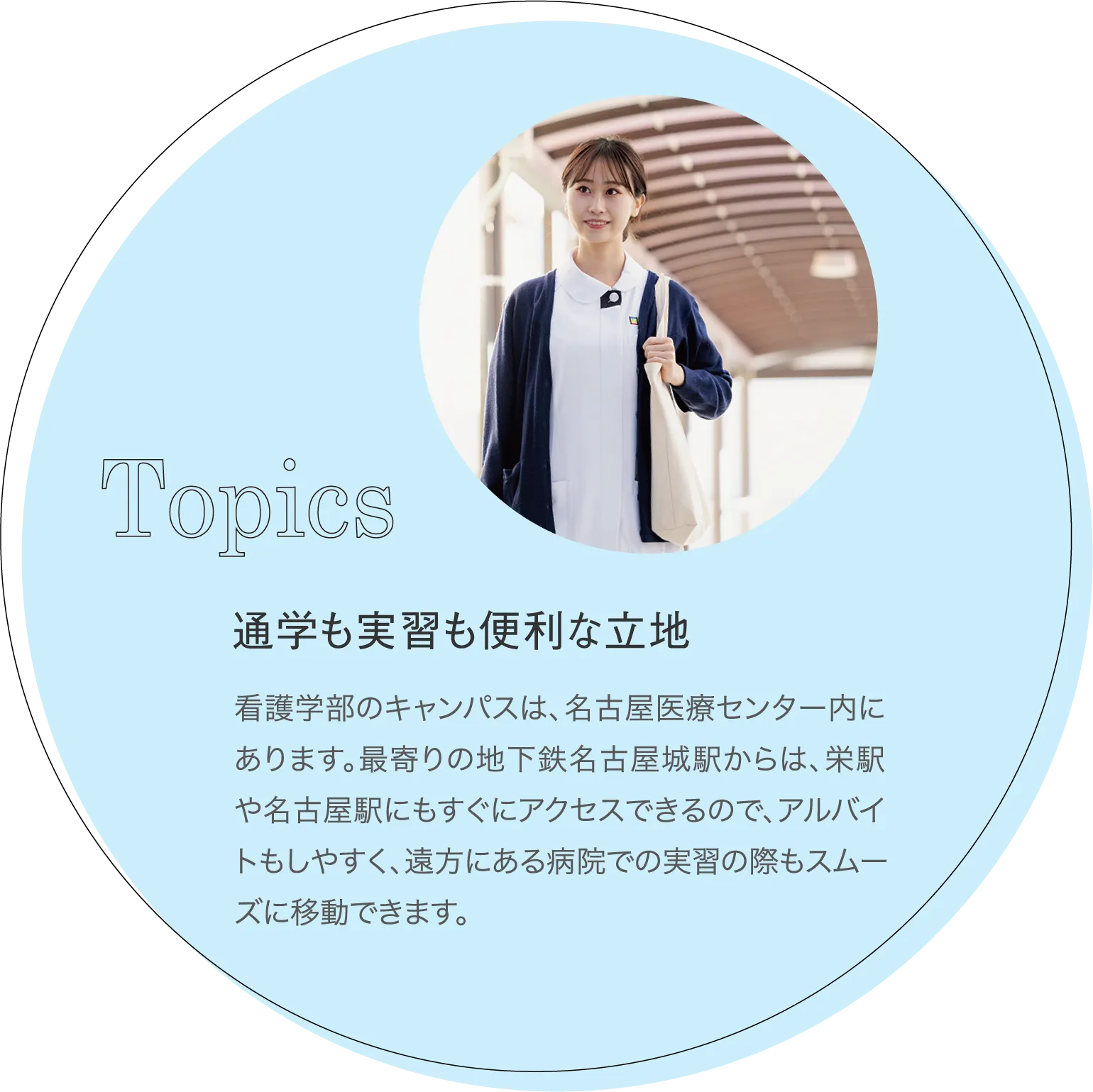
※掲載内容は在学時に取材した2023年2月末現在の情報です。
※2022年度入学生用のカリキュラムから内容が改定されているため、
現在のものとは開講時期や実施内容が異なる場合があります。