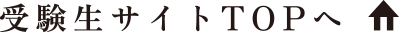- [取得資格]
-
- ●管理栄養士
- ●栄養士
- ●健康運動実践指導者
- ●食品衛生管理者(任用資格)
- ●食品衛生監視員(任用資格)


医療領域の学びに強い名古屋学芸大学なら専門的な知識まで深く学べると思い、入学しました。1年次には「人体生物学の基礎」、「人体の構造と機能」の授業で消化器の働きと栄養素の吸収について理解を深め、これらの知識と関連づけながら「調理学実習」で栄養価計算に基づいた調理に取り組みました。2年次の「臨床栄養学」では、管理栄養士としての倫理観から疾病別の栄養指導まで幅広く学び、病院で働く姿をイメージしながら授業に臨みました。




3年次からは、これまでに学んだ理論を実践する授業が中心になりました。例えば「応用栄養学実習」では「50歳男性」や「妊娠中期」など具体的な人物像を想定しながら、その人に合わせた献立を考えて実際に調理。献立を組み立てた背景や、どんな栄養素に注目したのか他の学生の前で発表することで知識が整理され、伝える力も身につきました。また、臨地実習では病院で働く管理栄養士としての仕事を深く学習。外来患者や病棟患者の栄養指導では、一人ひとりの性格に合わせたコミュニケーションをとるなど、カウンセリングスキルも求められると気づきました。4年次の卒業論文では、高齢者の咀嚼をテーマに取り上げました。地域の在宅高齢者の“噛む力”を強化することは病気の予防に役立つと考えており、研究成果を卒業後の病院勤務にも活かしていきたいです。


※掲載内容は在学時に取材した2024年2月末現在の情報です。




- [取得資格]
-
- ●管理栄養士
- ●栄養士
- ●食品衛生管理者(任用資格)
- ●食品衛生監視員(任用資格)
- ●健康食品管理士


1〜2年次は、人体、食品、栄養の基礎知識や調理技術、「管理栄養士特講(エキサイティング)」で管理栄養士の職務について学びました。高校では文系だったので、授業についていけるか不安でしたが、1年次前期の「基礎化学」や「生化学Ⅰ・Ⅱ」で、理系科目の復習をしっかりしたことで、その後の学びも自信を持って取り組むことができました。2年次になると、「臨床栄養学Ⅰ・Ⅱ」や大量調理を行う「給食管理実習」、食品メーカーの開発過程でも使用されている実験方法を学ぶ「食品学実験」の授業も始まり、自分に合う進路を考えながら、学びを深めました。




3年次以降は、2年次までの学びを発展させながら、学外での活動を通じて実践力を高めました。ゼミナールでは、名城大学女子駅伝部の栄養管理を担当。体重のコントロールや貧血など、個別の課題に対応しながら、寮や合宿先、遠征先で、献立作成や調理、栄養相談・指導に取り組みました。また臨地実習では、多様な診療科を備えた病院で、ICU(集中治療室)や緩和ケア病棟に入院されている患者さんの栄養管理、NST(栄養サポートチーム)業務を学びました。患者さんの命を支える管理栄養士の責任の大きさ、専門性の高さを再確認できたことで、「病院で働きたい」という意識が高まり、就職活動を迷いなく進めることができました。そして4年次からは国家試験対策もスタート。名古屋学芸大学ならではの「全員で合格するぞ!」という一体感のある雰囲気のなかで、仲間と支え合い先生に励まされながら集中して勉強に取り組めました。

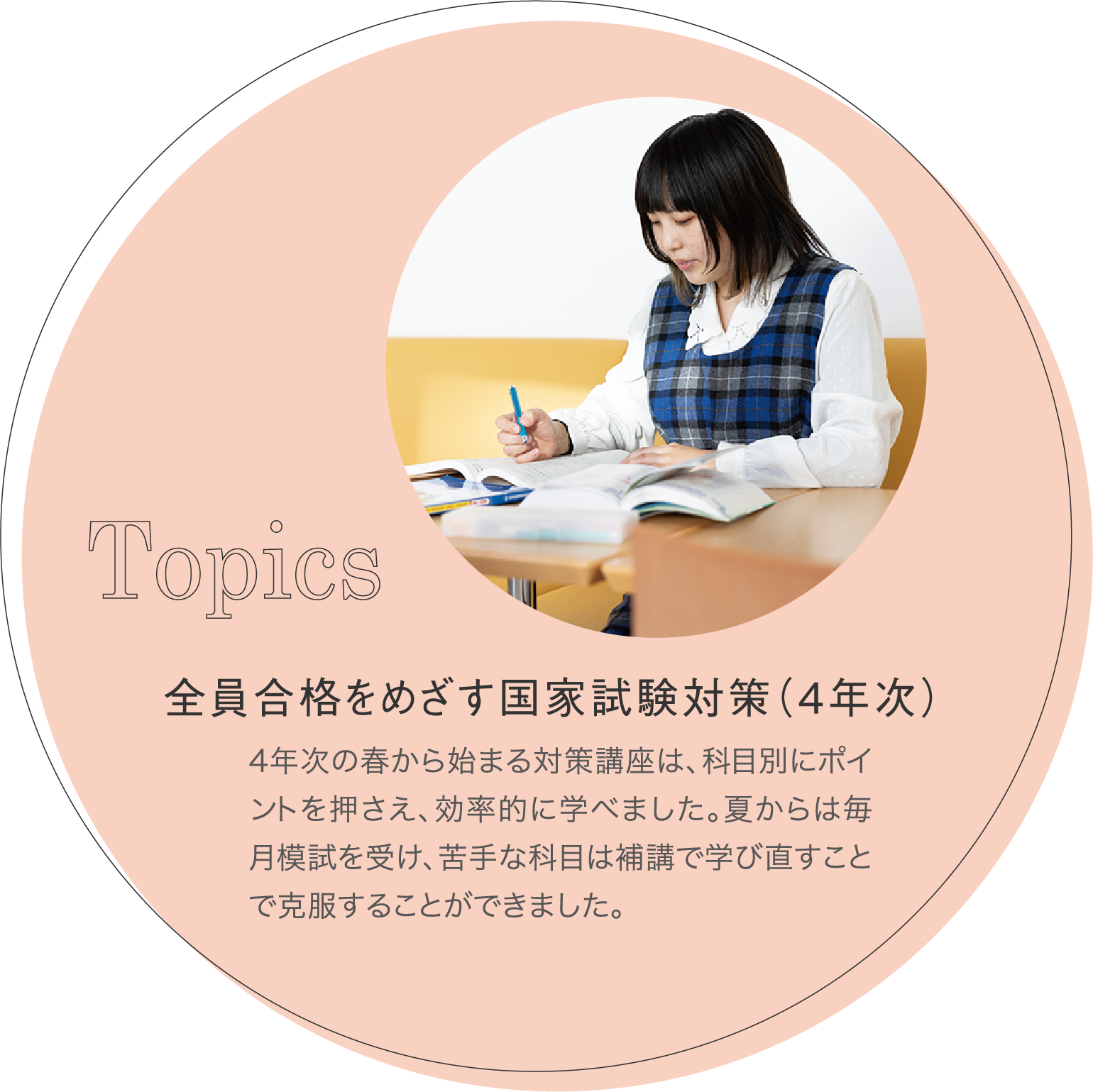
※掲載内容は在学時に取材した2023年2月末現在の情報です。